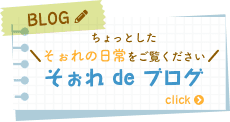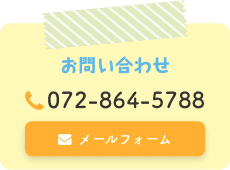経営法人

ごあいさつ

当社ホームページをご覧頂きありがとうございます。
2005年2月に枚方市長尾に「グループホーム そぉれ」をオープンし、お蔭様を持ちまして、節目の年である2015年2月に「グループホーム そぉれ」の新築移転、本社移転を無事迎えることができました。
今春行われた介護保険法改正で、介護をとりまく環境はよりいっそう厳しいものとなりましたが、私たちは、これからも、人として当たり前のことを優しく丁寧に行うという基本を実践し、チームとしてお困りごとには即応、柔軟にサービスの提供を行っていきたいと考えています。
今春行われた介護保険法改正で、介護をとりまく環境はよりいっそう厳しいものとなりましたが、私たちは、これからも、人として当たり前のことを優しく丁寧に行うという基本を実践し、チームとしてお困りごとには即応、柔軟にサービスの提供を行っていきたいと考えています。
そして、「認知症ケアの専門職」として地域に貢献できるよう今できる事を真面目に一つ一つずつ取り組んで参ります。
「そぉれ」という縁で結ばれた多くの方々に感謝申し上げ、今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
理念
経営理念
介護や福祉の仕事は、人の生命、生活を守る、尊い職業です。私たちは、その使命に熱い思いを抱き、誠実にサービスを提供します。また、介護、福祉の仕事に誇りを持ち続け、ともに働く喜びを感じられる、心の通い合う組織を目指します。
私たちウィズ・ケアサポートは、法令を守り健全な企業経営の下、相手を思いやる福祉の実践、未来へつなぐ人材の育成を通して、これからの住み良い地域社会へ貢献して参ります。
私たちウィズ・ケアサポートは、法令を守り健全な企業経営の下、相手を思いやる福祉の実践、未来へつなぐ人材の育成を通して、これからの住み良い地域社会へ貢献して参ります。
そぉれの基本理念
- お客様の立場で、ともに考えます。
- お客様に笑顔と感謝の気持ちで接します。
- チームワークで仕事に取り組みます。
経営法人概要
会社名
| 株式会社ウィズ・ケアサポート
|
代表者
| 大久保真紀
|
本社所在地
| 〒573-0163 大阪府枚方市長尾元町7-36-1
|
連絡先
| TEL:072-864-5788/FAX:072-857-0726
|
事業内容
| 【グループホーム事業部】
【在宅事業部】
|
設立
| 平成16年10月
|
資本金
| 1000万円
|